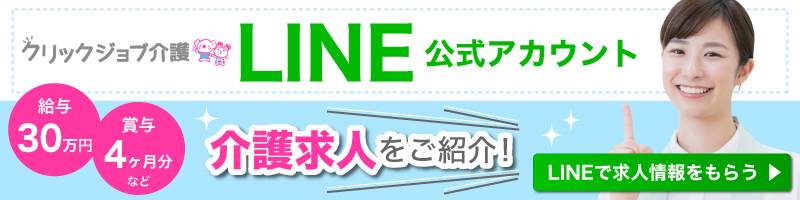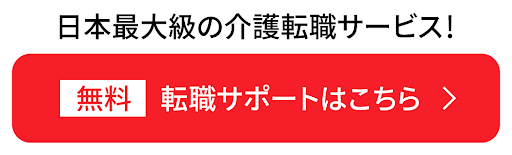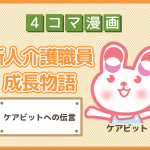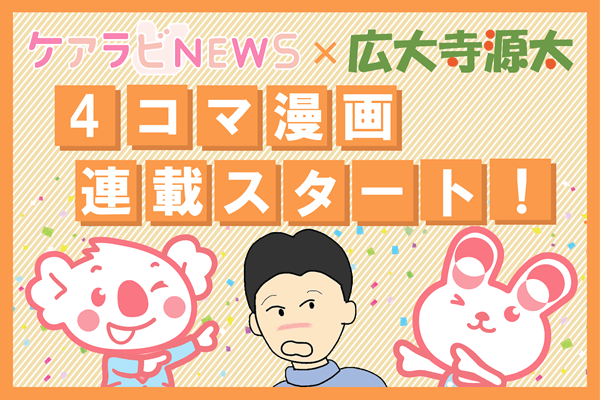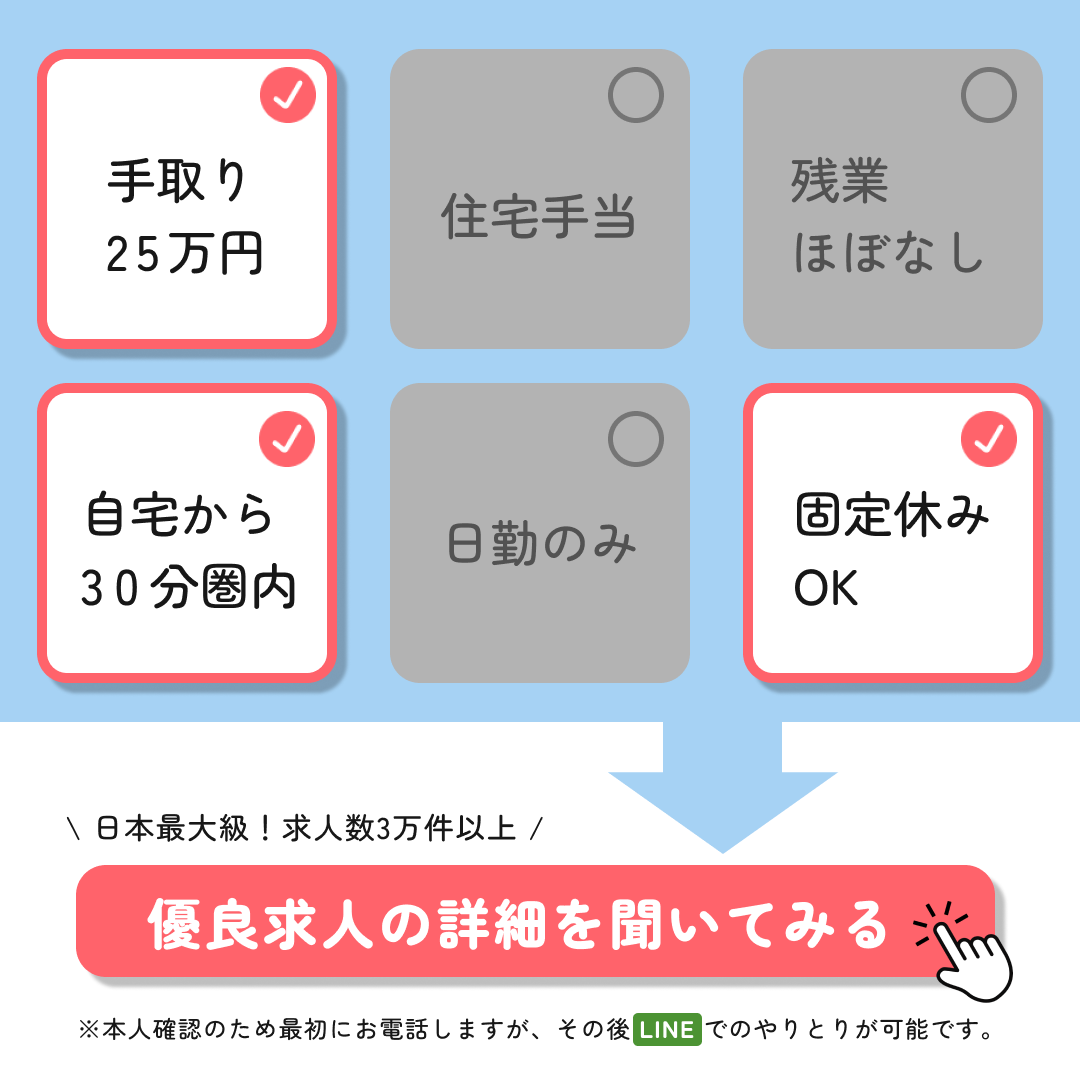耳で音を聞くだけではなく心と目でしっかりと受け止める「傾聴」。介護の現場では話しを聞くことは大切な仕事のひとつです。傾聴はどのようなことを言うのでしょうか。入所者さんから話を聞くときのコツとポイントをご紹介します。
「傾聴」とは?
米国の心理学者でカウンセリングの大家であるカール・ロジャーズ(Carl Rogers)によって提唱された「傾聴」。カウンセリング事例を分析し、話を聞くには3つの姿勢が大切だとしています。
1. 共感的理解:相手の立場になって共感しながら理解する
2. 無条件の肯定的関心:相手を評価・否定せず肯定的で好感を持った態度で話を聞く
3. 自己一致:わからない時はわからないことをはっきりさせながら理解して聞く
こうした態度で話を聞くことで、話をする人は安心した気持ちで相手に話をできるとされています。
相手の立場になり、気持ちを受け入れながら話すことで、相手は安心し、信頼関係が築かれていきます。相手の気持ちになり尊重することは、介護の仕事では大切なスキルとなるでしょう。
なぜ「傾聴」の姿勢が大切なの?
「きく」とは「聞く」「聴く」の二つの漢字があります。「聞く」はどちらかというと音が耳に聞こえてくる、音としてとらえて「聞く」という意味合いがあります。
それに対して「聴く」は、心をかけ、目と耳で「聴く」という意味合いがあるのです。
介護の現場での「傾聴」にはどのような意味があり、なぜ大切なのでしょうか。
年老いたシニア世代の人たち、介護の必要な人たちは、今の自分の姿やこれからのことについて悲観したりストレスを抱えたりしているものでしょう。
不安や不満があっても言葉の裏側に隠された本当の気持ちは、なかなか表現しない者です。または逆に、不安や不満を言葉にしていても本当の気持ちは、さみしさや辛さであるかもしれないのです。
介護者が苦しみや辛さを心と目と耳で「傾聴」することができれば、相手の心は自然と安心し、自分の心の整理を自分からするものなのです。傾聴することで相手の言持ちに寄り添い安心を得られた時、自ら生きる力を思い起こし、不安や不満を解決しようとするものなのです。
アドバイスをしたり結論を言ったりせず、ひたすら相手の話を心から聞くことが、入所者さんの生きる活力となるでしょう。
具体的な「傾聴」の方法とは?
それでは「傾聴」のポイントをおさらいしておきましょう。
否定をしないこと
話しを聞いているうちに、「それはどうなのかな?」と思うことがあっても否定をしてはなりません。もしかしたら話している入所者さんはそれを理解しながらも話してくれているかもしれないからです。
決して否定することなく、うなずきながらしっかり聞きましょう。
途中で話をさえぎらず最後まで聞く
話しを聞いているうちに、何が言いたいかわかっても、途中で話を止めたりこちらから先に結論を言うのはやめましょう。あなたの出した結論がたとえ入所さんの思う結論と同じであっても、途中で話をさえぎられた気持ちは大きなストレスとなるのです。
わかっても、話し終わるまでさえぎることなく聞きましょう。
表情やしぐさ、ジェスチャーで寄り添う
「そうだよね」「うんうん」と相槌をうち、その時の相手の気持ちに寄り添った表情で聞きましょう。こうすることでより「傾聴」の姿勢が伝わることでしょう。大げさにならないよう、ですが「聴いている・寄り添っている」と伝わる態度が大切です。
話が一区切りついたら、まとめる
だいたい話し終えたら、「〇〇ってことですよね。」と聞いた内容をまとめ、伝えましょう。話を理解したと言うことを伝えるためにも有効です。
傾聴スキルを磨こう
介護の現場で欠かせない「傾聴」の方法とポイントについてご紹介しました。傾聴のスキルはすぐに身につけるのは難しいかもしれません。まずは目を見てうなずき、話を聞くことから始めてみませんか。きっと信頼関係が築かれ、入所者さんとのコミュニケーション能力もアップするでしょう。