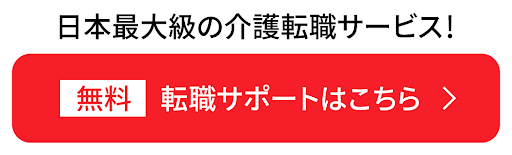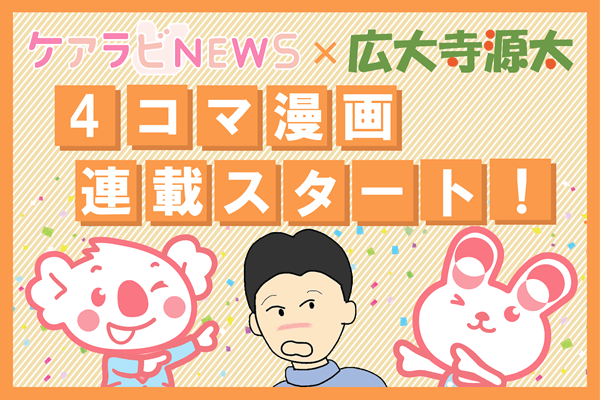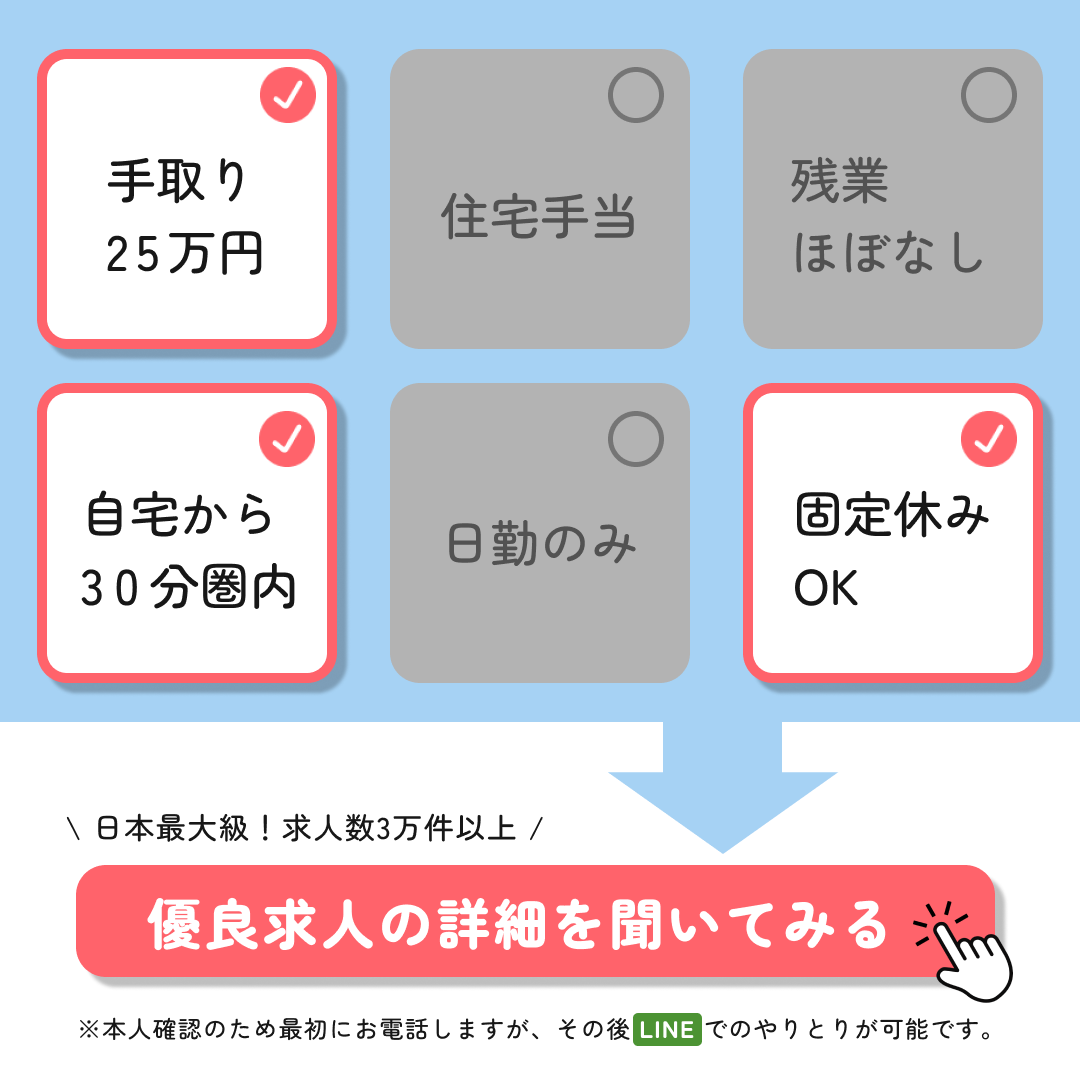理学療法士として三重大学附属病院に勤務した後、現在は映画監督として活躍中の榊原有佑さん。
異例の経歴をお持ちの榊原さんが原案・監督・脚本・編集を手掛けられた映画作品「栞」が、2018年10月26日より公開される。理学療法士の青年が主人公という榊原監督の実体験も反映された作品だ。理学療法士の頃の想いや、映画の制作背景についてお伺いした。

―理学療法士として働くようになって、ギャップを感じることはありましたか??
はい、ありました。当初イメージしていた理学療法士の仕事は、スポーツ分野の方のサポートなどが多いのかと思っていました。僕がサッカーでの怪我でお世話になったこともあって、イメージが偏っていたんだと思います。僕がイメージしていたことは、実際の現場ではほんの一部でした。
「筋肉や骨のことだけではなく、神経や脳など幅広い知識が求められる仕事なのだ」と専門学校に入ってから知りましたね。働くようになってからは、こんなに人と密に接する仕事なのかと、コミュニケーション能力も必要とされる仕事だと感じました。

―理学療法士のお仕事に就いてからの日々はどうでしたか?
喜びややりがいを感じる日の方が断然多かったです。ただ、入ったばかりの頃は大変でしたね。僕が勤めていたのは大学病院だったので、病状の安定していない方が多かったんです。患者さんが理学療法中に、亡くなってしまうという夢を毎日みてしまう時期もありましたね。急性期の方に接していくことに大きな不安を覚えて「自分が思っていたより、リスクの高い仕事なんだ」と感じました。

―2年間のご経験の中で、一番印象に残っていることはありますか?
「栞」の中では、葛藤や苦しみのシーンが多いかと思うのですが、実際の臨床経験でも難病患者さんを担当することも多くありました。
まだ治療法がない症例の時は、過去の事例を知りたくて、文献をたくさん取り寄せましたが、自分の求めている情報を見つけることはできなくて、目の前の患者さんを助けたいけれど、どうすることもできないこともありました。やりがいや、喜びの方が数でいったら断然多いです。ただ、強く印象に残っていることとなると「もうちょっと何かできなかったかな」という後悔の気持ちですね。

―映画監督になりたいと思ったのはいつですか?
昔から映画は好きだったので、高校の頃「映画が好きだから、映画監督になろうかな」位のテンションで思ったこともありました。でも「そんなの無理だよ」と周囲の言葉を受けて「あ、そうか」と当時は、すぐ進路変更しましたね(笑)正直、理学療法士になってからは、自分が映画監督になりたいと思っていたことも忘れていました。
―映画監督になろうと行動に移されたのはなぜですか?
知ってもらうことの大切さを改めて感じたからだと思います。以前、“アイス・バケツチャレンジ”ってありましたよね。ALSとも言われる筋萎縮性側索硬化症の研究を支援するための活動です。進行していくしかない病気の治療をするため、薬を開発するお金を募金してもらわないといけない。そのためにはまず知って頂かなければいけないですよね。
ALSも当初は知っている人の方が少ない病気でしたけど、活動によって多くの募金が集まりました。世の中には、苦しんでいる方や困っている方、支援を必要としている方はいるけれど、まずそのこと自体を知らない方達だらけだと、何もできないという状況があることに気がつきました。「このままじゃだめだな、もっと外に発信したい」と強く思いました。

また、2008~2009年頃ってちょうど高齢化社会についてもフォーカスされはじめて、医療保険を改正する動きもありました。でも、国の医療費負担だけで解決するのは現実的に難しいと感じたんです。この状況を、もっと知ってもらわないといけないなと。理学療法士をやりながら、ジャーナリストになろうかと文章を書く練習をしていた時期なんかもあったんです。
その頃、どんどんインターネットが普及してきていて、YouTubeなどで誰でも情報を映像で発信できる時代がくるなと。それなら、何ができるかわからないけれど、自分が撮影して編集するための技術を身につけようと思ったんです。

―仕事を変えることに、迷いはありましたか?
それがなかったんですよね。今まではあまり冒険せず、安パイを切るタイプだったのに不思議です。
理学療法士を目指していた頃から、漠然と「現場での臨床以外のこともしていかないといけない」とは感じていました。
実習などを通して、病院は外の世界と隔離されているような雰囲気もあると思ったからです。「もっと病院内での出来事を、外に伝えていかないといけない」と発信することの必要性を感じていたからかもしれません。
―周囲の反対はありませんでしたか?
反対は、めちゃめちゃされました。大学病院に就職できることは、名誉なことでもあったので「せっかく就職できたのに辞めるなんて」と言われましたね。実は映画「栞」を撮った後に、やっとお世話になった専門学校の先生に謝りに行けました(笑)

―映画監督になるまで、どのように過ごされましたか?
まずは映像の学校に通って、映像の制作会社に入りました。ただ「栞」のプロデューサーとは学生時代に知り合っていて「映画をやろうよ」と何回かお誘い頂いて、まずは助監督として映画業界に入りました。そこから1年ほど助監督として20作品ほどの現場に参加して経験を積んでいきました。そして2013年に短編映画を監督する機会をいただき、映画監督としてデビューすることができました。
「栞」に関しては2014年の年末だったと思うんですけど、たまたま居酒屋で、自分が理学療法士として勤めている時の話をすることがあって「それを脚本におこしてみてくれないか」と。そこから撮影までの2年半位は、構想を練ってずっと脚本を書いていましたね。
―完成した映画「栞」を観た時に、どんな気持ちでしたか?
実際に僕が患者さんに言われたことや、あの時自分がこう言えたらよかったと感じていることも作品にしているので「自分自身がこの映画に1番救われたのかもしれない」と感じましたね。

―この映画を1番観てほしいのは、どんな方たちですか?
理学療法士の映画ってほとんどないと思うのですが、医療関係者の方だけに向けて創ったつもりは全くないんです。本当にこういう業界のことを知らない人たちにこそ、観てもらえたらと思います。「絶対にこう感じてほしい」というシーンはなくて、むしろ「観た方によって色々感じて頂けるようにしよう」という点を強く意識して創りました。まっさらな状態で観て頂けたら嬉しいです。
―なぜ「栞」というタイトルにされたのでしょうか?
脚本を執筆している時に、ふと登場人物の何人かが本に挟む「栞」のような状態であると感じました。ある人はまだ続きがあるのに、ある時点で栞を挟み、本を閉じてしまう。ある人は1回閉じたその本から栞を抜き取り、次のページへと本をめくっていく。この「栞」が多くの登場人物の人生とリンクした時に、この作品のタイトルにしようと思いました。
また「栞」の漢字の意味について調べてみると、山道で木の枝を折り道標にしていたことが由来だそうです。最後のシーンで雅哉がとった行動が、自分がこの映画を創ったことが、誰かの道標になってくれるように願いも込めました。

―映画を拝見し、それぞれのキャラクターや会話のリアルさに驚きました。脚本を書く上で意識したこと等があれば教えて下さい。
ありがとうございます。脚本を執筆しているとドラマチックな展開や台詞が幾つか浮かんできます。しかしフィクションの映画とはいえ、自分の経験したあの臨床現場の中で有りえない台詞や描写は全て削除しました。そこの判断はやはり実際に経験していることが大きな助けになりましたし、脚本を書くにあたり多くの人に取材もさせて頂いたことでより明確になったと思います。
しかし、それだけでリアリティのある映画が創れるわけでもありません。撮影の前に役者さんと一緒に実際の患者さんを交えてお話しをさせてもらいましたし、病院に理学療法の見学にも、実際の学会にも行きました。ありとあらゆる入念な準備はしましたが、最終的には本番での役者の演技力次第です。出演している役者陣の演技は本当に素晴らしかったですし、自信を持って本作の見どころの一つだと言えます。

―苦悩・葛藤が中心に描かれている作品ですが、榊原監督自身が過去の経験や生活の中で壁にぶつかった際に、意識していることや実践されていることはありますか?
自分が今活動している業界では、努力したからといって期待通りの結果を得られるとも限りません。むしろ、そうでないことの方が多いです。医療福祉の現場に携わる人は真面目な人が多いので、それこそ自分自身を必要以上に責めてしまうこともあると思います。自分はそれで、1回立ち直れないほど苦しんだことがあります。
禅の言葉ですが「因果一如」という言葉を大切にしています。今日、自分にできる最善を尽くしていることが、その時点で素晴らしい結果なんだという考え方です。苦悩を抱えていようが葛藤していようが、今の自分にできることは「誠実に最善を尽くせるかどうか」だけだと考えています。壁にぶつかった時ほど、多くを求めず期待せずに「因果一如」を意識して実践しています。
―読者の方々へメッセージ
最近では、介護業界もどんどん社会に知られていっていますよね。どの業界も同じだと思うのですが、まず知ってもらうことで様々な可能性が広がると思います。医療も介護に就く人も、みんな「誰かの役に立ちたいとか、こんな○○がしたい」という気持ちを持って働き始めたと思うんです。もし、忙しさの中でそういった気持ちが置き去りにされてしまったり、変わらなければいけない環境があったりするなら、まずは知ってもらうことから始まると思います。
僕も、この映画一つで何かが大きく変わるとは思っていないです。正直一人の力には、限界はあるんですよね。でも数の力は絶対にあると信じています。理学療法士は、全国に約16万人いて、もし仮に半分の8万人が映画を観て何かを思ったり、少しでも意識が変わったりしたら何かしら変化があると思うんですよ。もちろん数の力を生むのは映画だけではないので、それぞれができるちょっとしたことが繋がって、大きな輪にしていくことができたら良いですよね。

■S61.6.30生まれ 愛知県出身様々な映像分野で幅広く活動。映像制作に必要な技能全てを身につけ元理学療法士という特異の経歴から得た感性を武器に、独自の世界観を作り上げる次世代監督。
2012年より映画製作会社 and picturesに所属し本格的に映画監督としての活動開始2013年に初監督を努めた短編映画「平穏な日々、奇蹟の陽」はShortShortFilmFestival2014&AsiaJAPAN 部門ノミネート、主演の有村架純がベストアクトレスアワードを受賞している。